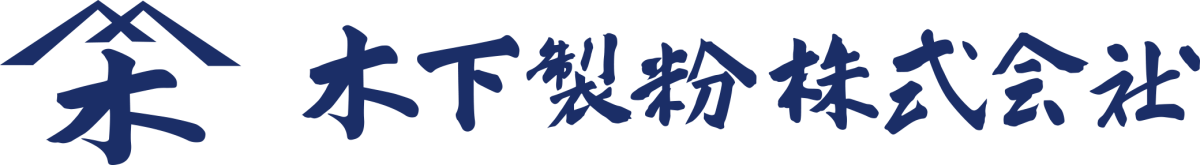#942 高松市うどん3冠V2達成
 地元紙(四国新聞)に「うどんの支出額・高松2年連続『3冠』」なる記事が掲載されました。これは総務省による都道府県庁所在地及び政令指定都市(52都市)を対象とした2024年家計調査の結果です。これによると高松市は1世帯(2人以上)当たりのうどん関連の支出3部門(①日本そば・うどん(外食)②生うどん・そば③乾うどん・そば)すべてにおいて2年連続首位となりました。高松市のうどん3冠は、2000年以降では11回目。また日本そば・うどん部門は24連覇、生うどん・そば部門は25連覇継続中です。
地元紙(四国新聞)に「うどんの支出額・高松2年連続『3冠』」なる記事が掲載されました。これは総務省による都道府県庁所在地及び政令指定都市(52都市)を対象とした2024年家計調査の結果です。これによると高松市は1世帯(2人以上)当たりのうどん関連の支出3部門(①日本そば・うどん(外食)②生うどん・そば③乾うどん・そば)すべてにおいて2年連続首位となりました。高松市のうどん3冠は、2000年以降では11回目。また日本そば・うどん部門は24連覇、生うどん・そば部門は25連覇継続中です。
 それぞれの支出額は画像の通りですが、特に外食については、16156円と全国平均の2倍以上。コスパに優れたさぬきうどんは、単価が安いものの、そこは来店回数でカバーし、堂々のトップとなりました。また生うどん・そばの支出が多いのは当然としても、乾うどん・そばの支出額が多いのが少し意外でした。というのも乾うどんは、一般にゆで時間が長いため、手っ取り早い生うどんを購入するケースが多いものと勝手に思い込んでいました。しかし乾麺には乾麺独自の良さがあるため、その食味食感が評価された結果かもしれません。
それぞれの支出額は画像の通りですが、特に外食については、16156円と全国平均の2倍以上。コスパに優れたさぬきうどんは、単価が安いものの、そこは来店回数でカバーし、堂々のトップとなりました。また生うどん・そばの支出が多いのは当然としても、乾うどん・そばの支出額が多いのが少し意外でした。というのも乾うどんは、一般にゆで時間が長いため、手っ取り早い生うどんを購入するケースが多いものと勝手に思い込んでいました。しかし乾麺には乾麺独自の良さがあるため、その食味食感が評価された結果かもしれません。
乾麺は昭和の最盛期には年間35万トンを記録したこともありますが、近年は19万トン程度で推移しています。ただこれは乾麺人気が落ちたというよりも食の多様化によって好みが分散化されたと考えるのが自然です。つまり近年は製造、保存、輸送それぞれ段階において技術革新が進み、冷凍うどん、チルド麺などの利便性簡便性に優れた商品が台頭し、その結果、常温長期保存が可能な伝統食品である乾麺が減少しました。小麦粉食品は、ざっと小麦粉1万トンが国民1杯分に相当する勘定なので、乾麺は毎月1~2回はそうめんやうどんとして誰もが食していることになります。
うどん以外の上位アイテムとしては、揚げかまぼこ(2位)はうどんのトッピングとしての需要、またかき(2位)やぶり(4位)は、香川県で養殖されていることが理由だと考えられます。逆に支出額が少ないアイテムとしては、傘(ワースト2位)、野菜(ワースト2位)、米(ワースト3位)などがあります。傘のワースト2位は降水量の少ない瀬戸内式気候の影響、そして米のワースト3位は、うどんの影響と考えるのが自然です。また野菜(ワースト2位)は、隣近所からのいただきものが多いことが、一因ではないかと勝手に思っています(個人的感想)。
ところで県外に目を向けると、例年御当地グルメとして注目されるギョーザですが、2024年は、浜松市の年間支出額が4066円と、宮崎市の3517円、宇都宮市の2801円を抑え、2年連続で都道府県庁所在地と政令市のなかでトップとなりました。調査は、スーパーなどで販売されている生ギョーザや焼きギョーザが対象となり、外食や冷凍食品、中華料理店でのテイクアウトは含まれません。
また最近注目を集めているラーメンについては、山形市(2万2389円)がライバルの新潟市(1万6292円)、仙台市(1万5534円)を抑え、ダントツぶっちぎりの1位となりました。この山形市の支出額は、記録が残る2000年以降の最高額となり、「ラーメンの聖地」をうたい、官民一体でPRに取り組んだ成果です。山形といえば杉板で作った浅い箱に盛り付けた板そばも有名で、山形県は長野県と並ぶ知る人ぞ知るそば処です。山形の知人と話していると、そばやラーメンといった麺文化を標榜する自信が端々に感じられます。幸いさぬきうどんは、今や全国区となりましたが、私たちうどん県民はそれにあぐらをかくことなく、一層気を引き締め、粗製濫造を戒め、品質重視の姿勢を再認識せんといかんなあと感じる今日です。