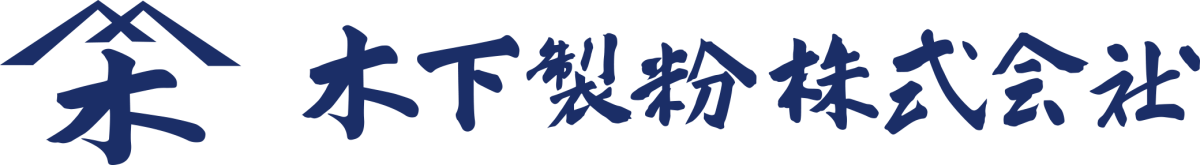#943 「パン入門〈改定2版〉井上好文著」①・・・日本のパンの歴史
 本書の初版は2010年ですが、この度改定第2版が発刊されましたので、ご紹介いたします。タイトルは「パン入門」とありますが、実際はパンの歴史に始まり、製パンの基本と基礎理論、各種製パン方法、パン材料、代表的なパンの種類とその製造方法等パンに関する内容をほぼすべて網羅した非常に密度の濃い内容となっています。製パンに関しては素人同然ですが、興味深い点をいくつか備忘録を兼ねてまとめてみました。
本書の初版は2010年ですが、この度改定第2版が発刊されましたので、ご紹介いたします。タイトルは「パン入門」とありますが、実際はパンの歴史に始まり、製パンの基本と基礎理論、各種製パン方法、パン材料、代表的なパンの種類とその製造方法等パンに関する内容をほぼすべて網羅した非常に密度の濃い内容となっています。製パンに関しては素人同然ですが、興味深い点をいくつか備忘録を兼ねてまとめてみました。
小麦の歴史は1万年以上も昔に遡り、またエジプト時代にパンは既に存在していましたが、日本にパンが伝来したのは、その遥か後のことです。1543年に種子島に漂着したポルトガル人が、その後九州地方を拠点にキリスト教、鉄砲とともにパンを日本人に伝えたとされています。日本語のパンは、ポルトガル語のpãoに由来しますが、当時のパンがどのような代物であったのかその詳細は不明です。ただ残念なことにパンはブドウ酒、キリスト教に密着していた理由で、日本で普及することはなく、1613年キリスト教禁止令、1639鎖国令により一旦幕を閉じます。
 パンが日本で普及するのは、それから200年以上後の江戸末期から明治維新にかけてです。1842年、伊豆韮山代官である江川太郎左右衛門が兵糧食(ひょうろうしょく)としてパンに関心を持ち、日本人として初めてパンの試作を行ったとの記録があります。よって同氏が日本パンの祖と呼ばれています。その後は1860年代になると横浜で数店のベーカリーショップがオープンしますが、対象は外国人および軍用と限定的でした。しかし明治時代に入り、文明開化を迎えるとパンの普及が徐々に進み始めます。
パンが日本で普及するのは、それから200年以上後の江戸末期から明治維新にかけてです。1842年、伊豆韮山代官である江川太郎左右衛門が兵糧食(ひょうろうしょく)としてパンに関心を持ち、日本人として初めてパンの試作を行ったとの記録があります。よって同氏が日本パンの祖と呼ばれています。その後は1860年代になると横浜で数店のベーカリーショップがオープンしますが、対象は外国人および軍用と限定的でした。しかし明治時代に入り、文明開化を迎えるとパンの普及が徐々に進み始めます。
契機は、銀座に木村屋というパン屋をオープンした木村安兵衛が、当時の日本人の嗜好にあった酒種あんパンを開発し、それを1875年に明治天皇に献上したことです。その後はお馴染みのジャムパン、クリームパンなどの日本人の嗜好にあった菓子パンが次々と開発され、パンは徐々に普及していきます。しかし主食となる食事パンへの普及にまでは至らず、第二次世界大戦が終了するまでは、日本におけるパン消費量は低く、食生活においてはあくまでも脇役にとどまります。
しかし第二次世界大戦後の10年間でパン消費は一気に加速します。その理由は戦後の食糧難に対処するためにGHQ(連合国軍最高司令部)が小麦や小麦粉を支援し、その小麦粉を基に配給パン工場や家庭委託パン工場がパンを製造し、消費者に提供したからです。1956年からは米の受給状況が改善されたために、パンの消費量は一時減少しますが、1962年からはライフスタイルや食の欧米化が進んだ結果、パンの消費量は右肩上がりで伸長しました(画像参照)。
 戦後のパン文化は、当初は米国の影響を強く受けましたが、1980年頃からは食パン類の高品質化、日本独自の菓子パン類の進化、惣菜パンの普及、さらにはフランス、ドイツ、デンマークなど欧州のパン類導入も進み、今日では世界でも類を見ない多種多様なパン製品が市場にあふれています。
戦後のパン文化は、当初は米国の影響を強く受けましたが、1980年頃からは食パン類の高品質化、日本独自の菓子パン類の進化、惣菜パンの普及、さらにはフランス、ドイツ、デンマークなど欧州のパン類導入も進み、今日では世界でも類を見ない多種多様なパン製品が市場にあふれています。
ところで私たちの主要穀物には、米、小麦、大麦などがありますが、これら主要穀物の摂取量はこれまで下図のように推移してきました。主要穀物(米+小麦+大麦)の合計摂取量は148.8kg↓83.3kg(約56%)と大きく落ち込みましたが、これは食生活が豊かになり、副食の割合が多くなった結果です。驚くべきことに、お米の摂取量は114.9kg↓51.5kgと半分以下、また大麦に至っては8.3kg↓0.3kgと大きく落ち込んだのにもかかわらず、小麦は25.8kgから31.6kgへと増加し、その後も横ばい状態で踏ん張っています。このような経緯を考えると、小麦は今や私たちの食生活には不可欠で、今後とも私たちの食生活を強く支えてくれるはずです。