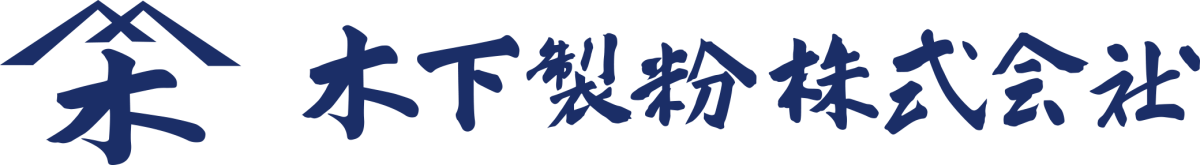#948 生成AIで世界はこう変わる(今井翔太著)
 今さらながらの感はありますが、遅ればせながらタイトル本を読んでみました。生成AIとは、テキスト、画像、音声、動画などのコンテンツを自動で生成する人工知能のことです。インターネット上で公開されている膨大なデータを学習し、パターンを解析することで、新しい情報を生み出します。たとえば文書生成AIは、膨大な文書から文法や語彙、文章の構造などを学習し、それに基づいて新たな文章を生成します。同様に、画像生成AIは、大量の画像から色彩や形状、テクスチャなどのパターンを学習し、それを基に新たな画像を生成します。
今さらながらの感はありますが、遅ればせながらタイトル本を読んでみました。生成AIとは、テキスト、画像、音声、動画などのコンテンツを自動で生成する人工知能のことです。インターネット上で公開されている膨大なデータを学習し、パターンを解析することで、新しい情報を生み出します。たとえば文書生成AIは、膨大な文書から文法や語彙、文章の構造などを学習し、それに基づいて新たな文章を生成します。同様に、画像生成AIは、大量の画像から色彩や形状、テクスチャなどのパターンを学習し、それを基に新たな画像を生成します。
 実際にコマンドラインから生成AIに対してプロンプト(質問文や指示文)を入力すると、あたかも向こう側にいる専門家とやりとりをしているような錯覚に陥ります。尋ね方を工夫するとそれなりにキチンとした回答が返ってくるので、相手がAIとはわかっていても、ついつい「ありがとうございます!」とか「参考になりました!」などとお礼を言ってしまいます。本書では生成AIの背景にある技術について簡単な説明があります。しかし簡単な説明は、理解できても、どうしてそれが質問や指示に対する精緻かつ詳細な回答に結びつくのか、そこには大きな飛躍があるようで全く腑に落ちません。
実際にコマンドラインから生成AIに対してプロンプト(質問文や指示文)を入力すると、あたかも向こう側にいる専門家とやりとりをしているような錯覚に陥ります。尋ね方を工夫するとそれなりにキチンとした回答が返ってくるので、相手がAIとはわかっていても、ついつい「ありがとうございます!」とか「参考になりました!」などとお礼を言ってしまいます。本書では生成AIの背景にある技術について簡単な説明があります。しかし簡単な説明は、理解できても、どうしてそれが質問や指示に対する精緻かつ詳細な回答に結びつくのか、そこには大きな飛躍があるようで全く腑に落ちません。
いつも丁寧かつ詳細な回答が返ってくるAIですが、注意すべき点もあります。質問に対する回答はいつも自信満々なのですが、それが必ずしも正しいとは限りません。嘘の情報を出力することをハルシネーション(Hallucination)といいます。ですから見事な回答を鵜呑みにすることなく、それが正しいかどうかは、こちら側で検証する必要があります。しかしそれを差し引いても、見事な文章が瞬時に返ってくる事実はにわかには信じられません。読書感想文やレポートなども、こちらか感じた印象とかポイントを数点提示するだけで、あっという間に仕上げてくれるのは、正に革命的です。きっと先生方は、既に採点にご苦労されているのではないでしょうか。
生成AI技術は向上することはあっても劣化することはありません。よって今後益々精度は高まり、ハルシネーション問題は、早晩解決されるに違いありません。チェスのチャンピオンを破ったディープ・ブルー、また最も複雑なゲームとされる囲碁においてもAlphaGo(アルファ碁)は絶対的な強さを誇り、早々と人間との対局からは引退しました。人間の能力は加齢とともに劣化しますが、AIは賢くなる一方です。今後AIが賢くなりすぎて、どのような将来が到来するのか、誰も正確に予測できないところがちょっと怖い気がします。
本書中には「AIによって消える仕事・残る仕事」という興味深くかつ恐ろしいトピックがあります。そしてこの問に対しては、「高学歴で高いスキルを身につけている者が就くような賃金が高い仕事であるほど、コンピュータ/AIによる自動化の影響を受ける可能性が高い」と結論付けています。生成AI登場以前は、「スキルを必要としない低賃金の仕事ほど、コンピュータ/AIによる自動化の影響を受ける可能性が高い」という正反対の予想でしたので、生成AI登場のインパクトが如何に大きいかがわかります。今後、生成AIを上手に使いこなすには、つまり如何に望ましい回答を引き出せるかは、指示や命令を最適化するスキルであるプロンプトエンジニアリングが重要になってくるといいます。簡単に言うと、「上手に質問をする技術」です。
生成AIに「(Q) うどん店の寡占化、チェーン店化が進んでいるが、独立うどん店は存続できるか?」と聞いたところ、「(A)『昔ながらのやり方』で生き残るのは厳しい。しかし個性を活かしたブランド作りや、体験・オンライン販売を取り入れることで十分に勝機はある。①価格競争から脱却し『価値』で選ばれる店作り②地域密着型または専門特化型の戦略③リアル店舗+オンラインのハイブリッド経営が鍵。つまり『安くて早い店』ではなく、『わざわざ行きたくなる店』になれるかどうかが、生き残りの分かれ目。」とのことでした(まあ、当たり前と言ってしまえば身も蓋もありませんが・・・)。