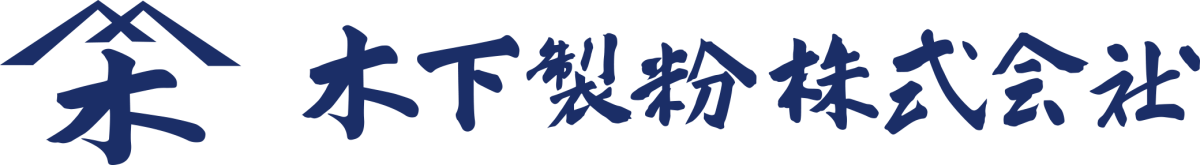#951 健康な人の小さな習慣(大平哲也著)
 疫学とは「医療」と「統計」を掛け合せた実践的学問。具体的には「病気が起こる原因や、どうやったら予防できるかということを、人の集団を対象として調べることにより明らかにする学問」のことです。個人ではなく、あくまで集団として捉え、その集団の特徴を調べます。言い換えると疫学とはできる限り多くのデータを集めて解析する学問であり、その対象となる数が多いほど、また期間が長いほど、その知見は蓄積されていきます。本書の表紙には、「10000人を60年間追跡調査してわかった」とあるように、本書の内容は10000人を対象に60年以上にわたり追跡調査を行い、そこから導かれた結論です。
疫学とは「医療」と「統計」を掛け合せた実践的学問。具体的には「病気が起こる原因や、どうやったら予防できるかということを、人の集団を対象として調べることにより明らかにする学問」のことです。個人ではなく、あくまで集団として捉え、その集団の特徴を調べます。言い換えると疫学とはできる限り多くのデータを集めて解析する学問であり、その対象となる数が多いほど、また期間が長いほど、その知見は蓄積されていきます。本書の表紙には、「10000人を60年間追跡調査してわかった」とあるように、本書の内容は10000人を対象に60年以上にわたり追跡調査を行い、そこから導かれた結論です。
 健康体になるための本書の結論は、至ってシンプルで以下の5原則に集約されます。つまりこの5原則が日本人の健康の最適解です。どれも言われてみると、なるほどもっともですが、実践できるかどうかは別問題です。巷には「◯◯を食べて健康に」とか「◯◯体操で健康」といったキャッチコピーが溢れていますが、単発的な行動だけで健康にはなれません。健康に特効薬はなく、「言うは易く行うは難し」、「健康に王道なし」ということでしょうか。
健康体になるための本書の結論は、至ってシンプルで以下の5原則に集約されます。つまりこの5原則が日本人の健康の最適解です。どれも言われてみると、なるほどもっともですが、実践できるかどうかは別問題です。巷には「◯◯を食べて健康に」とか「◯◯体操で健康」といったキャッチコピーが溢れていますが、単発的な行動だけで健康にはなれません。健康に特効薬はなく、「言うは易く行うは難し」、「健康に王道なし」ということでしょうか。
1.タバコを一切吸わない。
2.お酒は1日2合未満。
3.塩分を減らしカルシウムを増やした和食をとる。
4.座位時間を減らして適度な運動をする。
5.肥満を解消する。
本書には健康のためのエビデンスがごまんと紹介されていますが、「なるほど」と思った点をいくつかご紹介します。高血圧は健康寿命を縮めるリスク要因ですが、現在の高血圧の原因は、肥満が圧倒的です。つまり「食べ過ぎ⇒肥満⇒血圧上昇」というパターンで血圧が上昇します。実際、食べる量が多ければ、含まれる食塩も多くなるので、当然といえば当然で、肥満度と塩分摂取量は、きれいな相関関係を示しています。
高血圧には減塩指導が定番ですが、意外な方法として、「計測を習慣づけるだけで下がる」ということがわかっています。理由は計測して自覚をすれば、少しでも対策を打つようになるからだと言われています。体重も同様です。太っている人ほど体重計にのりたがりませんが、のらなければ気持ちが緩みさらに太るかもです。つまり毎日できる簡単かつ重要な仕組みが「計測」なのです。「血圧計」と「体重計」で毎日計測する単純な行為が効果的です。
またカリウムを含む食品の摂取も有効です。カリウムの効用は次の2つです:①カリウム自体に減圧作用があること、②ナトリウムは血圧を上げますが、カリウムを摂るとナトリウムが体外に排出されます(カリウムナトリウム拮抗)。カリウムはトマトを含めた緑黄色野菜、葉物野菜を生食することで摂取できます。また果物にもカリウムが多く含まれ、しかも果物をとるとうつ病リスクが下がることがわかっています。
意外なところでは、自治会の役員をすると死亡率が12%減少するという結果もあります。自治会役員は面倒臭いと思いがちですが、いろいろな人たちとやり取りし、頭も使うことが、健康に寄与するという理由です。またボランティア活動を行うと認知症や軽度認知症予防に効果があることもわかっています。集合住宅の管理組合の役員、PTA役員といえば「外れくじ」のように言われます。しかし「無償なのにやっていられない」と考えるのではなく、「お金を払わずに、大事なコミュニティと健康体を手に入れることができる」という発想の転換も大切です。他にも「笑うとストレスホルモンが30%減少」、「1週間に150分以上の有酸素運動」、「運動のためにわんちゃんを飼う」、「家は駅から15分がベスト」、「タワマンは健康に良くない」等など興味ある方はぜひご一読ください。